まずは海外駐在、本当におつかれさまでした。
帰国して少し落ち着いたころにふと「この子の高校どうしよう」「せっかくならICU高校も狙えるのでは」と考え始めた方も多いと思います。
一方でお子さんの英語はそこそこできるけれど実はペラペラというほどではなく内申点対策も手つかずで心の中はモヤモヤというケースもよくあります。
「ウチだけ準備が遅れているんじゃないか」という不安は心理学でいうバーナム効果の典型で実は多くのご家庭が同じ悩みを抱えているのに自分だけの問題のように感じてしまう心のクセでもあります。
この記事ではそんな親御さんに向けて実際に娘を帰国子女枠でICU高校に合格させた先輩夫婦として失敗も含めたリアルな体験と戦略をまとめていきます。
- 帰国子女枠でICU高校に合格したい家庭がまず確認すべき受験資格と全体像
- 海外で身についた英語力と入試で求められる英語のギャップ
- 帰国後の内申点を現実的に立て直すための考え方
- 英検準一級を目標に据えることで得られる具体的なメリット
- 帰国子女塾を「情報収集の基地」として賢く使う方法
- 帰国子女枠だけに頼りすぎたときに起こりうる最悪のシナリオ
- 海外駐在という権利と経験を受験にも人生にも活かす親のスタンス
帰国子女枠でICU高校に合格するためにまず押さえたい全体像
- ICU高校帰国子女枠の受験資格を確認する
- 帰国後から本番までのおおまかなスケジュール感
- 帰国子女枠と一般受験の違いを理解する
ICU高校帰国子女枠の受験資格を確認する
帰国子女枠でICU高校を目指すなら最初にやるべきことは塾探しでも過去問でもなく受験資格を満たしているかの確認です。
具体的には海外在住期間や帰国から受験までの期間在籍校の種別など細かい条件がありここがクリアできていないとどれだけ頑張ってもスタートラインに立てません。
まずは公式サイトや帰国子女塾の資料で条件をチェックし我が家が本当に「帰国子女枠の土俵」に乗れるのかを冷静に確認しておきましょう。
この段階で条件がギリギリの場合はどのタイミングで帰国させるかどの学年で受験させるかといった戦略にも関わってきます。
ここをあいまいにしたまま走り出すのは地図を見ずに山登りを始めるようなものなので最初にしっかり確認することをおすすめします。
帰国後から本番までのおおまかなスケジュール感
受験資格がクリアできそうだと分かったら次は帰国から本番までのざっくりしたスケジュールを描いてあげると全体像が見えてきます。
例えば中学三年の春に帰国する場合帰国直後は日本の学校生活と内申点の仕組みに慣れる期間夏から秋にかけては英検や模試を絡めた実力作り冬以降は出願と面接に集中というようなおおまかな流れです。
人はゴールまでの道筋が見えないと現状維持バイアスが働き「まあそのうちでいいか」と動き出しが遅れがちになります。
逆にざっくりでもロードマップが見えているとプロスペクト理論でいう「損失回避」の力が働き今動かないとチャンスを逃すかもしれないという健全な危機感が生まれます。
カレンダーにざっくりとしたマイルストーンを書き込むだけでも親子の視界が一気にクリアになるのでぜひ一度一緒に整理してみてください。
帰国子女枠と一般受験の違いを理解する
◆ココに写真◆
帰国子女枠は一般受験とはルールがかなり違いますが「楽に入れる裏口」のようなものでは決してありません。
試験内容は英語面接や作文が重視される一方で日本の学校での内申点やこれまでの学び方人柄も丁寧に見られます。
イメージとしては偏差値一本勝負のレースというより海外経験や思考力も含めた総合型選抜に近い入試だと考えるとしっくりくるはずです。
その意味で帰国子女枠はお子さんのストーリーを活かしやすい一方で準備なしに飛び込むと中途半端な状態のまま本番を迎えやすい入試でもあります。
一般受験との違いを理解したうえでどこを帰国子女枠ならではの強みとして伸ばしどこは一般受験と同じように地道に積み上げるかを親子で話しておくと戦略がブレにくくなります。
◆ココに広告貼り付け◆
英語力と内申点のギャップをどう埋めるか
- 海外で身についた英語と入試英語のズレ
- 帰国後の内申点を現実的に立て直す
- 英検準一級を目標にするという戦略
海外で身についた英語と入試英語のズレ
タイなどの現地校やインターで生活していると日常会話はそれなりにこなせるけれど文法やライティングに穴があるというケースが少なくありません。
ICU高校のような難関校では英語は「話せるかどうか」だけでなく論理的に書けるか読めるかといったアカデミックな力まで見られます。
ここを勘違いしてしまうとカタコトでも勢いだけで話せば大丈夫だろうと楽観視してしまい本番で「聞き取れるけど説明しきれない」という壁にぶつかりやすくなります。
とはいえゼロからやり直す必要はなく普段の英語生活に文法やエッセイを書く時間を少しずつ足していくイメージで十分間に合います。
海外で身につけた「生きた英語」に試験で求められる型をかぶせてあげることでお子さんの強みは受験英語に変換できると考えてください。
帰国後の内申点を現実的に立て直す
帰国子女枠とはいえ日本の中学校での成績つまり内申点は無視できません。
ただし万能感のあるオール5を目指す必要はなく狙う学校と教科配分によって「ここだけは落とせない」というラインを決めて逆算していくのが現実的です。
具体的には近所の個別塾などで定期テスト対策だけをピンポイントでお願いし提出物や小テストの管理は家庭で見ていくという二段構えが効果的でした。
我が家も最初は「帰国子女枠なら内申はそこまで見られないだろう」と油断してしまい痛い目を見たのでここは声を大にしてお伝えしたいところです。
内申点は一気に上がるものではなくコツコツとした積み重ねの結果なので早めに生活リズムと勉強習慣を整えておくことが何よりの近道になります。
英検準一級を目標にするという戦略
◆ココに写真◆
我が家がICU高校を目指すうえで打ち立てた一つの軸が「英検準一級を取る」という目標でした。
もちろん絶対条件ではありませんがこのレベルの資格があると書類選考や面接での説得力が一段違ってきます。
心理学でいう権威性の法則の通り第三者機関のスコアは一つの強い根拠となり面接官に「この子は英語で学ぶ準備ができている」と直感的に感じてもらいやすくなります。
また英検の勉強を通じて語彙力やライティング力を体系的に鍛えられるので帰国子女枠の試験と一般受験どちらにも効いてくるのが大きなメリットです。
英検をゴールではなくICU高校やその先の大学進学も見据えた「通過点」として位置づけると親子ともに前向きに取り組みやすくなります。
◆ココに広告貼り付け◆
帰国子女塾を「情報収集の基地」として賢く使う
- 帰国子女塾にしか集まらない合格データの価値
- 塾任せにして一度失敗した我が家の体験談
- 目的別に近所の塾や講座を組み合わせる
帰国子女塾にしか集まらない合格データの価値
◆ココに写真◆
帰国子女枠を本気で考えるなら帰国子女専門塾の情報ネットワークは正直かなり心強いです。
合格者の傾向や不合格だった生徒のスペックまで年ごとのデータが集まっているのでネット検索では絶対に出てこない生の情報を知ることができます。
これは心理学でいうウィンザー効果つまり本人の自己PRより第三者の情報の方が信頼されやすいという現象ともつながっていて実際の合否データほど親の腹をくくれる材料はありません。
我が家も説明会で「この内申と英検スコアなら過去にはこういう結果でした」という話を聞き戦略の軌道修正を決めたことが何度もありました。
帰国子女塾は授業だけでなく「情報のハブ」として活用するという発想で付き合うと費用対効果はぐっと高まります。
塾任せにして一度失敗した我が家の体験談
とはいえ帰国子女塾に通わせればすべてが解決するかというと残念ながらそんなに甘くはありません。
正直に言うと我が家も最初の年は塾をほぼパッケージで信じてしまい「このカリキュラムをこなしていけば何とかなるだろう」と半ば受け身で一年を過ごしてしまいました。
結果どうなったかというと本人の得意不得意とカリキュラムのギアが噛み合わず中途半端な実力のまま本番を迎えてしまい悔いが残る結果になってしまったのです。
今振り返るとこれはまさにコンコルド効果のようなもので「ここまで塾に投資したのだからこのまま最後まで乗り続けよう」と深く考えずに惰性で走り続けてしまっていました。
塾はあくまで手段であり我が家にとって本当に必要なメニューかどうかは親が定期的に立ち止まってチェックする必要があると身をもって学びました。
目的別に近所の塾や講座を組み合わせる
◆ココに写真◆
二年目以降は発想を変えて帰国子女塾は情報収集と志望校対策に集中させ内申対策や基礎学力は近所の個別塾にお任せするスタイルに切り替えました。
例えば定期テスト前だけ日本の教科書に強い個別塾で理社数を固め英検の直前期はオンラインの英検対策講座に絞って受講するなど目的ごとに最適な場を選ぶイメージです。
一見手間がかかるように見えますが実は松竹梅の法則のように「高いパッケージ」か「まったく使わないか」の二択ではなく中くらいのちょうど良い選択肢を自分たちで作り出す感覚に近いです。
結果的に子どもの負担も家計の負担もコントロールしやすくなり何より「この組み合わせはウチに合っている」という納得感を持って受験期を走り切ることができました。
塾を一つに決めるのではなくパズルのピースのように組み合わせていく発想を持つと帰国子女受験の戦略はぐっと柔軟になります。
◆ココに広告貼り付け◆
帰国子女枠に全ベットしない併願とリスク管理
- 帰国子女枠だけに頼ることのリスク
- ICU高校以外の併願校の考え方
- 「権利を最大限活かしつつ進路の幅を守る」親のスタンス
帰国子女枠だけに頼ることのリスク
◆ココに写真◆
帰国子女枠は魅力的な制度ですがここだけにすべてを賭けてしまうのは正直かなりリスキーです。
募集人数が少ないうえにその年の顔ぶれによってレベルが大きく変わることもありいわゆるバンドワゴン効果的に「みんな狙っているからウチも」と流されるだけでは足元をすくわれかねません。
もし帰国子女枠一本で準備を進め不合格になってしまうと一般受験の準備が足りず「とりあえず受かる学校」に流れてしまうという最悪のシナリオも現実的に起こり得ます。
これはお子さんにとっても親御さんにとっても精神的なダメージが大きくせっかくの海外経験がネガティブな記憶として残ってしまいかねません。
だからこそ帰国子女枠を最大限活かしつつも一般受験レベルの学力は地道に維持しておくという二本立ての発想がとても大切になります。
ICU高校以外の併願校の考え方
ICU高校が第一志望であっても併願校のラインナップは早めに検討しておくことをおすすめします。
帰国子女枠を設けている学校や英語教育に強い学校を複数ピックアップし我が家の価値観や通学圏と照らし合わせて「このあたりなら納得感を持って通える」という候補を持っておくイメージです。
このとき気をつけたいのは偏差値だけで並べるのではなく校風やカリキュラム帰国生の比率などお子さんが実際に通う姿を想像しながら選ぶことです。
心理学でいうフレーミング効果の通り「第一志望に落ちたから仕方なく行く学校」ではなく「海外経験を活かせる選択肢の一つ」として併願校を見せてあげるだけで子どもの受け止め方は大きく変わります。
親が併願校に対して前向きなストーリーを語れるかどうかは受験期のメンタルを支える上で意外と大きなポイントになります。
「権利を最大限活かしつつ進路の幅を守る」親のスタンス
◆ココに写真◆
せっかく海外駐在という貴重な経験をしてきたのですから帰国子女枠という権利はぜひ最大限活用してほしいと先輩夫婦として本気で思っています。
ただしその活用の仕方は「この一本にすべてを賭ける」ではなく「選択肢の一つとして活かしながら進路の幅も守る」というバランス感覚が大事です。
イメージとしては無人島に持っていくものを一つだけ選ぶのではなく救命ボートと非常食と地図をセットで持っていくようなものでどれか一つに頼り切らない準備が安心感につながります。
親がこのスタンスを持っていると子どもも「ICUに受かったら最高だけど別の道でもきっと大丈夫」と健全な心の余白を持ったまま受験に向き合うことができます。
最終的に進む学校がどこであっても海外で過ごした時間と受験期に親子で考え抜いたプロセス自体がお子さんの大きな財産になるはずです。
◆ココに広告貼り付け◆
帰国子女枠でICU高校を目指す家庭へのまとめメッセージ
- 帰国子女枠でICU高校を目指すなら最初に受験資格を冷静に確認する
- 帰国から本番までのおおまかなロードマップを親子で共有しておく
- 海外で身についた英語に試験向けの型をかぶせてギャップを埋める
- 内申点は早めの生活習慣づくりと定期テスト対策で地道に積み上げる
- 英検準一級など客観的な指標は権威性を生み受験全体を有利にする
- 帰国子女塾は授業だけでなく合否データが集まる情報基地として活用する
- 塾任せにせず我が家に必要なメニューかどうかを定期的に点検する
- 目的に応じて近所の個別塾やオンライン講座を組み合わせて戦略を組む
- 帰国子女枠だけに賭けず一般受験レベルの学力も維持しておく
- ICU高校以外にも海外経験を活かせる併願校を早めに検討しておく
- 第一志望に届かなくても経験自体が子どもの成長につながると捉える
- 海外駐在という権利は「特別扱い」ではなく「選択肢を増やす鍵」と考える
- 受験期の子どもを追い詰めるのではなく伴走者として支える姿勢を持つ
- せっかくの帰国子女枠という権利は遠慮せず最大限に活用してほしい
- どの学校に進んでも親子で考え抜いた時間が将来の大きな自信になる
◆◆文末広告◆◆
“`
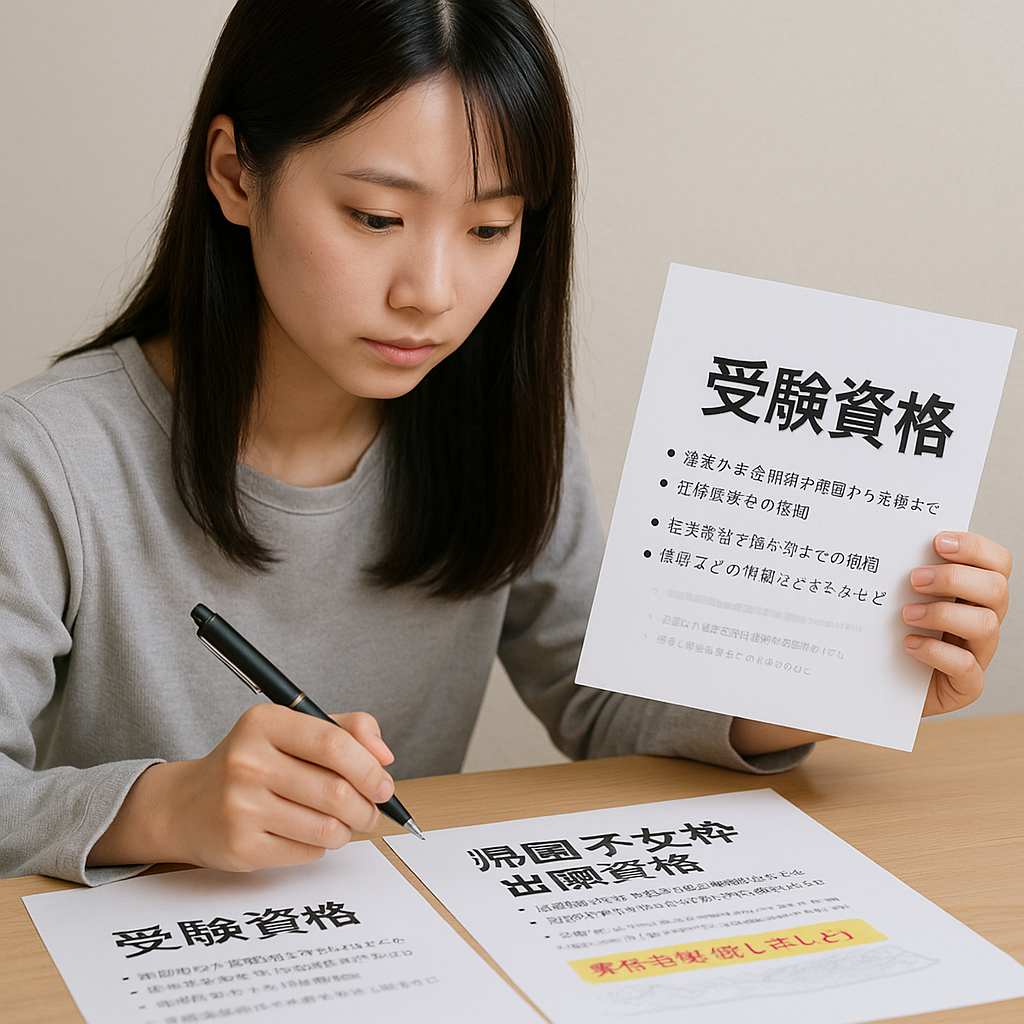
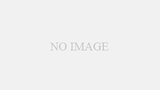
コメント